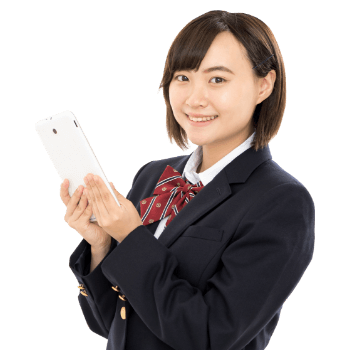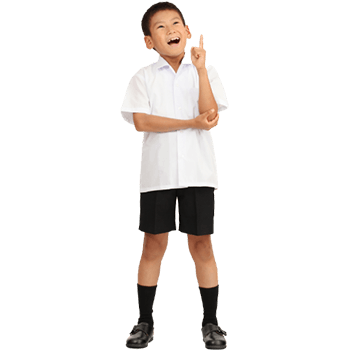-
2023.06.17
前向きに失敗しよう
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室
- 未分類
失敗は誰にでも起こることですが、 何度も失敗を繰り返すと辛く感じる事があります。 私も些細な失敗を連続して起こしてしまい、気持ちが落ち込んでしまう事があります。 しかし、前向きにとらえる事ができれば、失敗は何かにチャレンジしている証となります。 成功するために乗り越えなければならないものです。本当にそうなのです。これで辛いからといって行動を辞めてしまったら、成長する事はない。 失敗から学び、成長することは、自信をつけるだけでなく、自分が何をすればよいか理解するのにも役立つでしょう。新しいことにチャレンジする場合には、最初は失敗することがあるかもしれませんが、そこで何をすべきか、何が必要かといっ
-
2023.06.16
昆虫にも血は流れているが赤くない
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室
皆さんこんにちは。最近息子と昆虫取りに夢中な教室長です。 皆様、昆虫にも血液があることをご存知でしたでしょうか?そう昆虫にも血がながれているのです。 ただ、人間とは違い赤くないことがほとんどなので血が流れていないように見えているだけです。 人間の血液が赤いのは、血液中に含まれる「ヘモグロビン」が酸素に結びつくことで赤く見えるためです。 しかし、昆虫の血液にはヘモグロビンが存在しないため、ほとんどの場合血液は透明です。
-
2023.06.16
命題とは何か
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室
数学Ⅰで習う「命題」とはいったいなんでしょうか。言葉の意味が分かりづらいですね。 命題とは、物事が正しいか、正しくないかを明確にできる文章や式の事です。 これは「pならばq」(~ならば~である)のような形で表現されます。 例えば、「野球は球技である」というのは客観的に正しいため命題になりますが、 「野球はおもしろい」というのは主観的なので命題にはなりません。 もし命題が正しい場合は「真」であり、誤りの場合は「偽」となります。
-
2023.06.16
指数とはなんですか?
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室
「指数」とは、数字とか文字の右肩に乗せた小さな数字の事です。 同じ数字をたくさん掛けることを表しています。 例えば、2の3乗と書くと、2×2×2=8という計算を表します。 指数には法則があって、それを「指数法則」とも呼んでいます。 指数法則の一例をあげると、同じ数字の指数を掛け算するときは、指数を足して大きな指数にします。 例えば、2の2乗×2の3乗は、2の5乗となります(2×2×2×2×2=32)。また、数字を累乗するときに、1をかけたら元の数字になります。例えば、4の2乗×1=4の2乗です(4×4=16)。 基本的な3つの法則を覚えると、数学Ⅰの問題には対応できます。
-
2023.06.15
保護者の皆様へ、お子様の国語の教科書を読んでみてください
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室
保護者の皆様へ 個別指導WAM堺市駅前校です。 いきなりでございますが、私たちは国語の教科書を読むことをおすすめしています。小学校の教科書でも中学校の国語の教科書でもOKです。教科書は子供たちが感動や共感を持って読むことができる素晴らしい作品が詰まっている事を実感できるのではないでしょうか。 教科書には、小説や随筆や説明文。詩や童話など、様々な作品が記載されています。これらの作品は、子供たちが抱える悩みや問題に対して、深い考察や解決策を提供してくれる場合があるかもしれません。また、読むことで自己表現力や語彙力、文章力が向上し、国語力の向上にもつながるのではないでしょうか。 大人になった我々が読
-
2023.06.15
夏休みを充実させよう!
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室
今日は、夏休み期間中の過ごし方についてお話させてください!! 夏休み期間中は、時間に余裕があるため、新しいことに挑戦する絶好の機会となります。例えば、自分で興味を持った本を読んだり、好きな科目の勉強をしたり、自分が苦手とする科目を克服するために取り組んだり、音楽を聴いたりや絵をかいたり、友達と遊びにいったり、スポーツをするなど、自分の興味を追求することができます。 夏休み中は自由時間が多いので、ついつい遊んでしまったりすると思いますが、学習習慣を維持すれば、新しい学びの発見があるかもしれません。また、日常生活でも習慣化することで、睡眠時間や食事、運動などの健康にも良い影響があることもご存知でし
-
2023.06.14
昆虫の寿命を実感する
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室

昆虫にもいろいろ寿命があると思います。 4月、5月よりも6月はバッタやカマキリが増えてきました。 春から夏にかけた、これらの昆虫は明らかに秋のこれらの昆虫より小さい昆虫ばかり。 つまり、今のこれらの昆虫は生まれたばかりの昆虫で、これから脱皮を繰り返し大きくなるのでしょう。 春から秋にかけて、昆虫探し。楽しみです。
-
2023.06.14
不等式とは
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室
- 未分類
不等式は、等号(=)ではなく不等号を含む式の事を不等式と言います。 左辺と右辺の数の大きさを比べ大小関係を表します。 例えば、「x > 5」という不等式は、「xが5よりも大きい」という事です。また、「y ≤ 10」という不等式は、「yが10以下である」という事です。 では早速ですが、上記を理解できたという事で次の式を解いてみましょう! 「2x + 4 ≥ 10」という不等式を解く場合、以下のように解を求めます。 2x ≥ 10 – 4 2x ≥ 6 x ≥ 3 このように、不等式の両辺に同じ値を加算したり、同じ値を減算したりすることで、式を変形しながら解を求めます。 不等式は
-
2023.06.14
平方根とは
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室
今日は中学3年生で学ぶ平方根について簡単に説明致します。 平方根とは、ある数を二乗すると、その数になる値の事です! いきなり分かりにくい💦 例えば、2の平方根は1.41421356...という数になります。 この数を2乗すると2になります! 更に分かりにくい💦 少し分かりやすく。 例えば、4という数、これは2×2=4ということができます。 その逆に、4という数の平方根は2という数になります。(-2もあります) まずは4、9、16、25といった自然数の平方根を覚えると覚えやすいかもしれませんね。 ちなみに平方根を表すために√という記
-
2023.06.14
因数分解と展開
- 堺市駅前校
- 堺市
- 大阪教室
いったい因数分解とは何でしょうか?数学って難しい言葉が使われます。一つ一つ理解していきましょう。 因数分解とは小さな数のかけ算(因数)に分解することを因数分解といいます! たとえば、18を因数分解すると、2×3×3となります。つまり、18は2と3と3をかけたもので表せることが分かります。 他にも具体的な例としては、以下のようなものがあります。 12を因数分解すると、2×2×3となります。 24を因数分解すると、2×2×2×3となります。 また、数学では因数分解とセット学ぶ「展開」というものがあります。 展開とは()の中にある数式を分かりやすくする事です。 例えば、()の中に次のよ