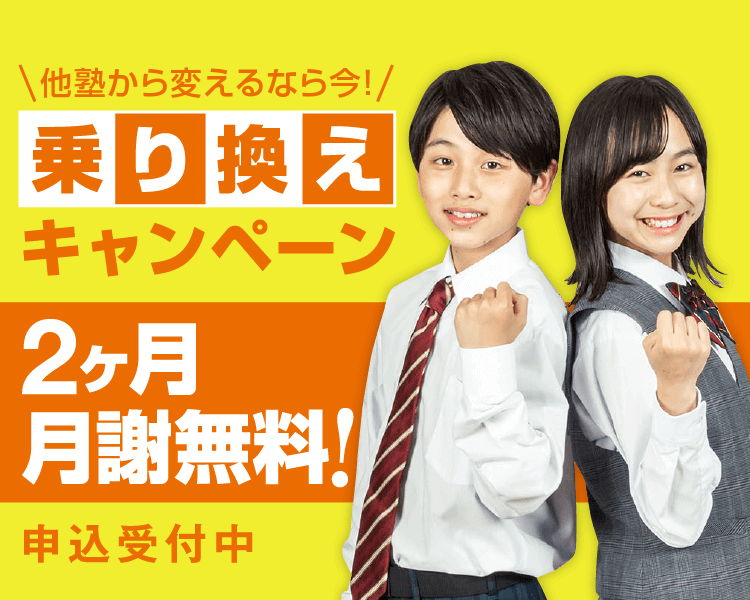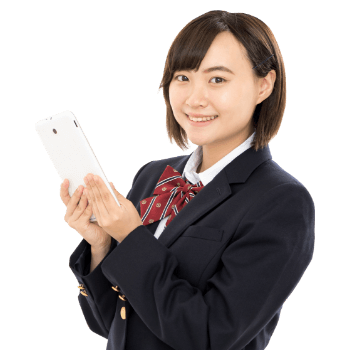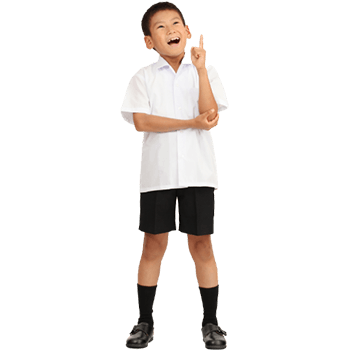教室ブログ
こんにちは、個別指導Wam藤の木校です。
春ですね。桜があちこちに咲いていて、勉強なんて放っておいてどこかに出かけたくなります。でも「春だから運動しよう」と言われても、「しよう!」と同意してくれる人もいれば、「えぇ?ヤだよ」と思う人もいるでしょう。
学校での体育の時間も同様です。教室ではいつもつまらなそうにしているのに、体育になるとやたら張り切る人もいれば、その逆に肩を落とす人もいます。体育は他の座学とは違いますよね。
得意な人はよいですが、苦手な人は苦痛でしかないでしょう。体育の成績がいつも悪いと憂うつになります。アスリートまでいかなくても、せめて成績をどうやって上げればよいのでしょうか。
いつも主要科目に関することを取り上げていますが、今回は副科目、しかも体育について。
運動が不得意な人は、「自分は生まれつき苦手に違いない」とか「得意な人とは脳の構造が違うのだろう」と思っているかもしれません。でもアスリートと一般の人との脳に違いはないですし、運動を司る部分は小脳ですが、小脳に遺伝的な違いはないようです。
では何が違うのでしょうか?
運動が得意な人と苦手な人との違いは、過去にどれだけ練習しているかの経験値が影響しているようです。人間は動物の中でも未発達のまま生まれるので、ハイハイも立つこと歩くことも、全ての動作がトレーニングによります。基本的な運動を行う能力は誰でも持っているのです。
一言で言えば、体育は頭ではなく「身体に覚えさせる」ことに尽きます。
例えばバスケットボールのゴールにボールを入れる場合、一般の人はなかなか入りませんが、アスリートはだいたい入るか、近いところにいきますよね。このように、一般の人は理想の動きと実際の動きの差(誤差)が大きくありますが、アスリートはほとんどない、いつもおおよそ理想的な動きをしています。言い換えると、一般の人は無駄な動きを多く行っていますが、アスリートは無駄がないのです。
ではその誤差を小さくするにはどうするか。答えはけっこう単純、練習すればよいのです。
「いや、練習しなくても初めから何でもできる(ようにみえる)子はいる」――確かにいますね、でもその子も、それ以前にさまざまな運動を経験していたのです。生まれながらのアスリートなんていないのです。
一般に幼少期に運動していたほど得意になります。「じゃあもう中学生になってしまったからダメだ」と思うのは間違いです。20歳くらいまでなら十分に取り戻せます。ただし幼少期の方が簡単で、歳を経れば経るほど難しくなります。例えて言うなら、10歳のときは10の努力で到達できたのに、12歳から始めると12の努力が必要になる、といったイメージでしょうか。努力は必要になるものの、別にアスリートにまでなる必要はないのですから、体育で合格点をとるくらいは頑張りたいところです。
もっとも、「居残り」や「追加練習」をしろと言われると確かに嫌だし、できれば避けたいし逃げたいですよね。でも屈辱に耐えられそうなら、「今やっておけば将来楽になれる」と思って(というより信じて)頑張りましょう。なかなか思えないと思いますが、ずいぶん先(50年後とか)に「あのときやっててよかった」と思うときが必ずきます。
一方、身体が覚えられても、運動し続ける持久力もまた必要でしょう。
運動は糖と酸素でエネルギーを造ることによって行っていますが、持久力は酸素をどれだけ吸えるかによって変わってきます。つまり酸素をたくさん吸える人ほど持久力があるのです。でも肺は自力では動くことができないので、周囲の様々な筋肉が動かないと呼吸自体ができません。裏返せば、腹筋などの筋肉を鍛えれば肺にたまった空気(二酸化炭素など)を吐き出すことができるし、出すことによって新しい空気をたくさん吸うことができ、結果持久力をつけることができるのです。
腹筋などの肺周りの筋肉を鍛えましょう。そうすれば持久走で横腹が痛くなることもなくなります。
そうは言っても、例えばとび箱など、足がすくみ緊張して、結果失敗してしまう人もいるかもしれません。それらを繰り返すと、「どうせやっても無駄ではないか」と思えてきますよね。でもそれは脳のエラーというか、脳が自動的に意識に介入して「思わせている」ことなのです。
人は「してはいけない」と考えると、そのことを考えてしまいしてしまうというシステムが備わっています。これを心理学では「皮肉エラー」といいます。例えば五円玉を糸で吊るし、「中央でピタッと止まる」と指示されるとできるのに、「左右に動かしてはいけない」と指示されるとできなくなる、という実験があります。このように、私たちはイメージしたとおりに身体が自然に動いたり反応したりする能力を持っていますが、「してはいけない」と考えても同じようにそのイメージが浮かんでしまい、ミスやエラーにつながってしまうのです。
ましてや「失敗すると恥ずかしい」「次は成功させなきゃ」とプレッシャーがかけられると、皮肉エラーを余計に助長してしまいます。だから失敗する、どうせダメだと思ってしまう・・・の悪循環になってしまう。それを逆手にとれば、成功するイメージを頭で描けばよいのです。失敗しても、「次は成功する」と思いましょう。
最初に言いましたように、体育は頭ではなく身体に覚えさせることが大切なのです。つまり成功するイメージだけ頭で描いて愚直に練習をしていれば、合格点くらいには到達するでしょう。
小学校中学校と、歳を経るほど思考は速く巡るようになり、周囲の反応もより気になってしまいがちです。耐えられず「居残り」には参加できなくても、例えば一人でこっそり夜にジョギングでも続けてはいかがでしょうか。そのときはあまり変わらなくても、後々やっててよかったと思うはずです。
かくいう私も体育はあまり好きではありませんでした。今になってもう少しやっておけばと思います。そう思わないよう、「身体に覚えさせる」ことを意識して、頑張りましょう。
【参考】
NHK「ヴィランの言い分」運動音痴(2024年7月20日放送)