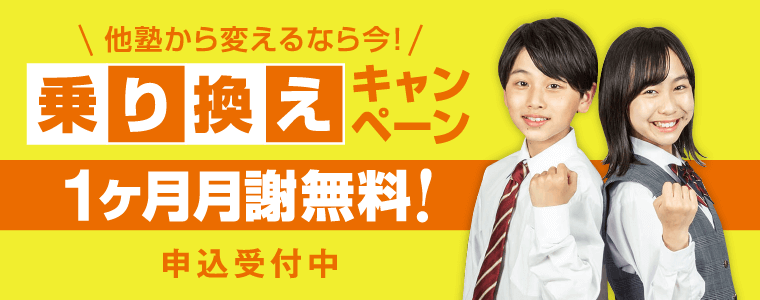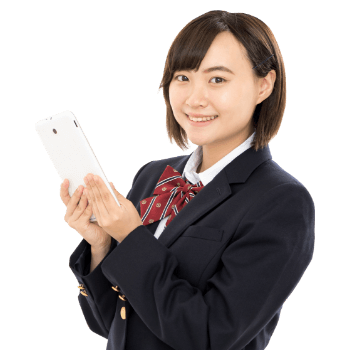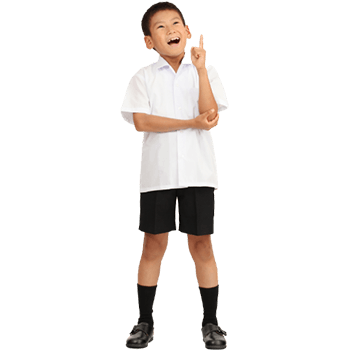教室ブログ
こんにちは!磐城駅前校です。本日も一人でも多くの方の目に届くことを願い、
投稿させていただきます。
前回の続きです。
前回の#2でお話した原因はほんのごく一部です。それ以外にも家庭環境や人間関係、経済観念や価値観など、様々な要因があり、今の若者のが「必要以上に不安を抱えている」という事が言えます。
この「不安」という状態を、人間はとても嫌がります。そしてその「不安が強い」状態を避けたい、逃げたい、軽減したい、と言う状態を作り出すために「スマホ依存」を引き起こしていると言えます。
この「依存」について、その目的は前述したとおりになりますが、この「依存」を「辞める・辞めてみる」という事が今回のお話です。
まず初めに「私は〇〇に依存している」という事に気付くところから始めましょう。気付くという事は「ありのままを受け入れる」という事です。
その事自体に善し悪しの判断をしないで、ただそこにあるモノとして取り扱うという事です。それが出来て初めて「依存していることに気付く」という事が出来ます。
「これが難しいんだよ」と言う気持ちはわかります。しかし人間は往々にして「無意識に」ともすれば「いつの間にか」依存しているというケースが大半です。
自分からわざと「お酒に依存してやろう」と思う人は少ないと思います。大体の大人が「最近ストレスが多くてつい酒に逃げているうちに依存してしまった」と言うでしょう。
つまり、「依存」とは「目的」になりえないという事です。目的は別にあり、その結果としての「依存」が起きているのだと理解して下さい。
依存とは段階がありますので簡単にご紹介します。
まずは「日常生活に支障をきたしている場合」これは確実に依存をしていると言っていいでしょう。つまり「それが無いと日常生活を送る事が出来ない」と言う状態です。
このような深い依存は「病気」に該当します。従って医療機関に相談する事をお勧めいたします。
次に、「それが無いと不安がせりあがってくる感覚。ソワソワ・ザワザワする感覚がある」場合。これも依存している可能性があります。スマホ依存もこれに該当するかもしれません。例えば「定期的にSNSをみて身辺チェックをする」や「ショート動画をながらで見て気が付いたら1時間が経過している」など。自己チェックをしてみましょう。
最後は「それがあると気が晴れて次も頑張ろうと思える」状態、これは依存ではなくそのモノとうまくお付き合いが出来ていると言えます。例えば「月一回のご褒美に甘いお菓子を食べる」や「たまの贅沢に美味しいお酒でほろ酔いになる」などは問題ありません。
何もかもを「依存」とみなし、恐れる必要は無いという事ですね。
次回に続きます。
葛城市・大和高田市の塾
個別指導 Wam 磐城駅前校
黒田 裕亮
〒639-2164 葛城市長尾275-16 川西ビル1F
TEL : 0745-44-3779