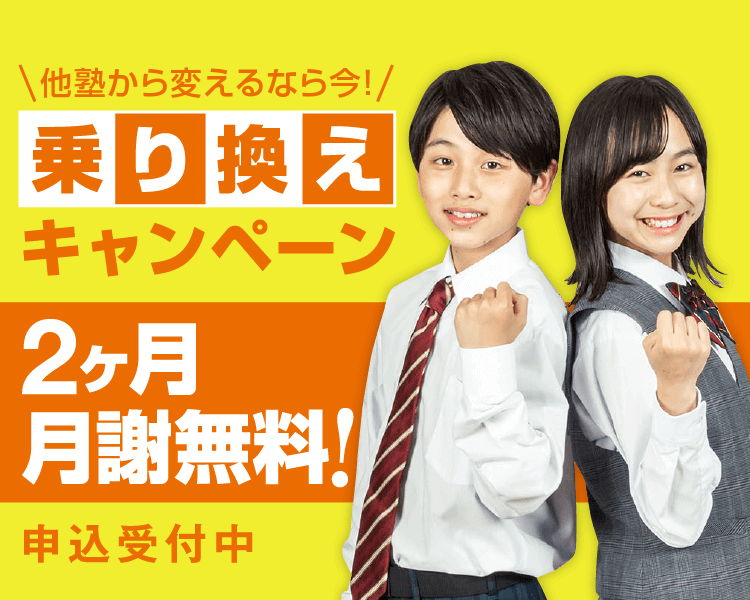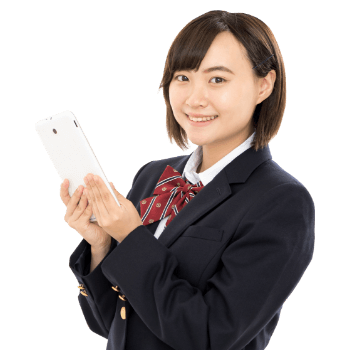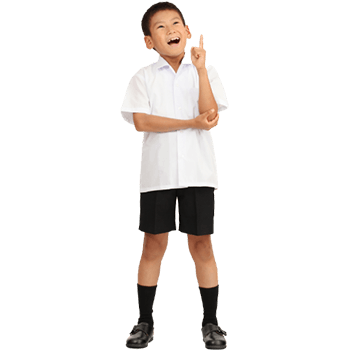教室ブログ
こんにちは、個別指導Wam藤の木校です。
入試の季節ですね。受験生は落ち着かない日々を過ごしておられるかと思います。受験生に限らず、テストは嫌なものですね。特にバツが多いと。。
でも「テストが終わった・・・微妙な点数だった・・・」で終わってはいませんか。実は、テストは見直してこそ意味があるんです。やりっぱなしや、点数をみて終わりではもったいない。
同じように見えているバツですが、実はバツには四種類もあります。そのバツに応じた対策を自分で行うことによって、成績は確実に上がります。
「いや、模試で送られてくる分析資料は目を通してるし」という人も多いかもしれません。ですが、残念ながら模試業者がいくら細かく分析しても、自分で行う見直しには敵わないのです。
ではバツの四種類ってなんでしょう? そして、そのバツによってすべき対策ってなんでしょう?
ますは1.注意不足バツ。
いわゆるケアレスミスです。細かくいうと、入力ミス/油断ミス/出力ミス/時間配分ミスといろいろあります。
・入力ミスとは読み間違いのこと(テスト用紙から頭への入力を間違えるミス)。
・油断ミスとは、暗算して間違えるなどの計算ミスや、いつもは省略して書いている漢字などをテストでも省略してしまうなどのミス。
・出力ミスは解答欄を1問とばして書いていたり記号で書くのに語句で書いたりするミス。
・時間配分ミスは字のごとく一問に時間をかけ過ぎて間に合わなくなるなどのミスです。
これらをひっくるめて注意不足バツ、ケアレスミスといいます。
ケアレスミスというと「なんだケアレスミスか。大丈夫、次は注意するから間違わないだろ」と鼻で笑う人がいます。いやいや、この「注意不足バツ」の問題点の一つは、いつも同じ(あるいは似た)ミスを繰り返してしまうことにあるのです。
「次は間違わないだろ」と思ってしまうあなた、本当に間違わないですか? いや、確かに次は間違わないかもしれません、が、次の次は(忘れて)やっぱり間違うかもしれません。このようにミスが毎回とは限らず、3回に1回とか10回に3回くらいかもしれないのがこの注意不足バツの厄介なところです。
「注意不足バツ」の問題点のもう一つは、本来正答できるはずのところで点数を取り逃がしていることにあります。理解の度合いを試すのがテストの目的なのに、注意不足で落とすなんてもったいないじゃないですか。
対策としては、自分がどんなケアレスミスをするか知ること、そして同じケアレスミスをしないように意識することです。そうすることで、同じような(似たような)ミスを繰り返さなくなる、少なくとも頻度は下がるでしょう。
次に2.解答をみたらわかるバツ。
解答をみたら、「何だそうか」と次回から解けそうと思えるミスです。
でも「次回から解けそう」と思えても、いざ挑戦してみると解けないものです。それに、全く同じ問題はできても少し変えた類題はわからないかもしれません。
この「解答をみたらわかるバツ」の問題点は、「わかって」いるけど「できて」いない、解き方は知っているけど身についていない、言い換えると基礎を用いる発想力が不十分、ということです。
対策としては、類題(数字だけが違う問題など)を解いてみる、そして基礎の問題から応用問題、発展問題など、関連する問題を数多くこなすことです。そうすることで、問題を見たらどう解けばよいのか発想できるようになるでしょう。
一番厄介なのが3.思い込みバツです。
これは、間違って理解していることに気づいていないミスです。「当然正解しているに違いない」と思っていた箇所でバツになっていて、見直して初めて「え?なぜバツ?」と驚くので、一見1.注意不足バツと思うかもしれません。
「思い込みバツ」の問題点は、自分では見つけにくい/気付きにくいだけでなく、どうしてバツなのかもわからないということにあります。問題から模範解答まで丁寧にみて、ようやくわかることもあれば、それでもわからないこともあります。そうなると自分では直せないので、人に頼らなくてはいけません。
対策としては、「思い込みバツ」の解答をよく読み、時には教科書を見直して、バツの原因をじっくり見極める必要があります。それでもわからないときは、人(先生、友達)に訊く以外ないでしょう。少し手間ですが、それで改めて正しく理解することで、以降正答できるようになるでしょう。
最後は4.解答をみてもわからないバツ。
これは何のテストかによって大きく二つの場合があります。一つは入試や模試などの応用・発展問題が多いテストの場合。もう一つは定期テストなど基礎の確認を中心としたテストの場合です。
前者(模試など)は、基礎はわかっていても解説が不親切だったりやたら難解だったりで、解答をみてもよくわからないことがあります。これも誰かに聞くしかないものの、基本的に対策は2.解答をみたらわかるバツと同じです。
問題は後者(基礎中心のテスト)です。このテストで解答をみてもよくわからないバツは、その単元の内容が十分に頭に入っていないミスになります。このミスの問題点は、まず改めて「知る」ところから始めなくてはならないため、時間がかかることです。従って対策としてはその単元の教科書を見直すことになりますが、それでもわからなかったら、わかるところまでさかのぼる必要があります。面倒ですが、「抜けているところがわかってよかった」と思いたいですね。ですがそうすることで、解ける問題が大きく増えることになります。
さて四種類のバツをみてきましたが、気付いたでしょうか、自分ではおよそ「これは解答をみたらわかるバツだな」とか「これはうっかりミスかな」とかわかるものの、自分以外の人にはわからない、ということを。また、テストが終わってから時間が経ってしまうと、自分でも記憶があいまいになってしまうかもしれません。
それに、テストのときはよくわからなくてテキトーに答えたけど、たまたま正答してた、という場合もあるでしょう。「どうせ間違っていると思っていたらマルだった」わけですから3.「思い込みバツ」の逆ですね。その場合はラッキーではありますが、次はわかって正答したいものです。
それも3.と同様対策しなきゃいけませんが、なんにせよ、やはり自分で見直ししなくては始まりませんし、またバツだけを見直ししていても不十分、ということもわかると思います。
結果にショックを受けているあなた! 点数だけで判断せず、どういうバツだったかをきちんと見直し、それに応じた対策をしていくことが、次につながります。次こそ満点を目指しましょう。FIGHT!
【参考】